
高齢者が使う補聴器
これがよく行方不明になるのです。
今の補聴器は
・身に付けても邪魔にならないように
・補聴器だとまわりに気づかれないように
超小型化しています。
だからこそ、いったんなくすと探すのがとても大変なんです。
なんども補聴器をなくす親になにか対策はないのでしょうか?
高齢の親が補聴器を失くす時の対策

高齢の親御さんが補聴器をなくしてしまうとのこと、ご心配ですね。
補聴器は小さく高価なものであり、高齢になるにつれて着脱や管理が難しくなりmす。
そのため、紛失のリスクは確かに高まります。
以下に、具体的な対策を詳しくご紹介します。
①補聴器を失くす主な原因を理解する**
対策を講じる前に、なぜ親御さんが補聴器をなくしてしまうのか、その原因を把握することが重要です。考えられる原因としては、以下のようなものがあります。
- 着脱時の落下
食事、入浴、着替え、あるいはマスクやメガネの着脱時などに、不意に外れて落ちてしまう。 - 置き忘れ
外した後に定位置に置かず、様々な場所に置き忘れてしまう(テーブル、ベッド、ポケットなど)。 - 操作の難しさ
小さな補聴器の操作や手入れが億劫になり、外したまま放置してしまう。 - 認知機能の低下
どこに置いたか忘れてしまったり、管理がおろそかになったりする。 - 補聴器のフィット感
耳に合っていない補聴器が外れやすい。
これらの原因を踏まえ、以下の対策を組み合わせて行うことをお勧めします。
②具体的な補聴器紛失防止対策
出は具体的な親のホ著いう気を失くす対策を考えていきましょう。
a) 保管場所の固定と習慣化(組織的・行動的対策)
- 「補聴器の家」を作る
補聴器を外したら必ず置く場所、いわば「補聴器の家」を決めましょう。充電器一体型のケースであれば、そこを定位置とします。場所は、親御さんが日常的によく過ごす場所で、目につきやすく安全な場所が適しています。
(例:リビングのサイドテーブル、寝室のナイトテーブル) - 定位置に戻す習慣をつける
補聴器を外す際は、「補聴器の家に戻す」ことを繰り返し声かけし、習慣づけを促します。難しい場合は、ご家族がそばにいる時に着脱のサポートを行い、一緒に定位置に戻すようにします。 - 外出時の「一時的な家」を決める
外出先で一時的に外す場合のために、専用の小さなポーチやケースを用意し、バッグの中の決まった場所に入れるようにします。
b) 落下防止グッズの活用(物理的対策)
補聴器が耳から外れても、そのまま落下して紛失するのを防ぐためのグッズが市販されています。
補聴器と衣服の襟元などをクリップで繋ぐものです。万が一補聴器が耳から外れても、ストラップでぶら下がるため落下や紛失を防げます。
片耳用と両耳用があります。
デザインもシンプルなものから、ビーズなどが付いたアクセサリー感覚のものまで様々です。親御さんの好みや使いやすさに合わせて選びましょう。
耳かけ型補聴器だけでなく、耳あな型補聴器でも取り出し用のテグスにリングを通して使用できるタイプもあります。
メガネを使用している場合は、補聴器とメガネの両方を繋げられるストラップもあります。
これらの落下防止グッズは、補聴器販売店やオンラインショップ(Amazon、楽天市場など)で購入可能です。「補聴器 落下防止 ストラップ」「補聴器 イヤチェーン」などで検索してみてください。
c) 補聴器本体と装用の確認(物理的・行動的対策)
- フィット感の確認
補聴器が親御さんの耳に合っているか、定期的に補聴器販売店で確認してもらいましょう。耳の形は変化することもあり、フィットしない補聴器は外れやすくなります。必要に応じて、耳型を取って作るオーダーメイドのイヤモールド(耳栓部分)を検討するのも有効です。 - 正しい装用方法の確認と練習
補聴器を正しく耳に装着できているか確認し、難しい場合は一緒に練習を行います。特に新しい補聴器にした場合や、操作が不安な場合に重要です。補聴器販売店でも装用指導を受けることができます。 - マスクやメガネとの干渉を避ける
マスクの着脱時やメガネとの位置関係で補聴器が外れやすくなることがあります。マスクのゴムは補聴器の上からかける、メガネのツルは補聴器の内側(頭側)になるようにするなど、外れにくい装用方法を一緒に確認しましょう。
d) テクノロジーの活用(技術的対策)
比較的新しい補聴器には、スマートフォンと連携できるものがあり、紛失時に役立つ機能を持つものがあります。
それは紛失防止機能・位置情報サービスです。
スマートフォンのアプリと連携することで、補聴器との接続が最後に確認された場所を表示できる機能を持つ補聴器があります。
これにより、どこで紛失したかの手がかりが得られる場合があります。ただし、リアルタイムで追跡できるわけではない点に注意が必要です。
親御さんがスマートフォンを利用している場合や、これから補聴器の買い替えを検討される場合は、このような機能があるか補聴器販売店に相談してみるのも良いでしょう。
e) ご家族など周囲のサポート
- 声かけと協力
補聴器を外す際に「補聴器、大丈夫?」「ここにしまおうね」など、定期的に声かけを行います。ご家族など周囲の人が、補聴器の管理を一緒にサポートする体制を作りましょう。 - 外すタイミングの管理
入浴前や就寝前など、補聴器を外すタイミングで声かけや確認を行います。
③もし紛失してしまったら
万が一補聴器を紛失してしまった場合は、以下の行動をとります。
- 心当たりのある場所を徹底的に探す
まずは家の中や最後にいた場所など、可能性のある場所を家族総出で丁寧に探します。 - 警察に遺失届を出す
見つからない場合は、最寄りの交番や警察署に遺失届を提出します。補聴器には製造番号が控えられており、警察と補聴器販売店、メーカーが連携して落とし主を探す取り組みが進められています。 - 購入した補聴器販売店に連絡する
購入した販売店に紛失した旨を連絡しましょう。製造番号から情報をたどれる可能性や、紛失時の保証(購入時の契約による)について確認できます。
高齢の親御さんの補聴器紛失を防ぐためには、一つの対策だけでなく、複数の対策を組み合わせることが効果的です。
保管場所の固定と習慣化を基本とし、落下防止グッズの活用、そして補聴器のフィット感や正しい装用方法の確認を行います。
必要に応じて、紛失防止機能のある補聴器や、ご家族のサポートも検討しましょう。根気強く続けることが大切です。
これらの対策を通じて、親御さんが安心して補聴器を使用し、快適な聞こえを維持できるようサポートしていきましょう。
親が補聴器をよく失くす場所は?

「母さん 補聴器はどうしたの?」
補聴器を付けていない親に大声で聞いてみると
「わからん。どっか いってしもた・・・」
と蚊の鳴くような声で返事をしてききます。
補聴器は最低でも軽く十万円以上もする高価な代物です。
それを何度も無くされてはたまったものではありません。
補聴器を失くす場所はいつもいるところ?
補聴器をなくしやすい場所って別に特別な場所じゃないんです。
補聴器をよくなくす場所は
「自宅」
「畑」や「庭」
などが多いのです。、
自宅で何気なくちょっと補聴器を外したのだが。それが見つからない。
ただでさえ高齢者の家の中には物がいっぱい溢れています。
その散らかった中から小さな補聴器を探し出すのは至難の業なのです。
また意外と多いのが「畑」や「庭」です。
畑仕事していて・・・
庭いじりをしていて・・・
つい熱中してしまってどのあたりで補聴器wなくしたか?分からないことも多いのです。
失くした補聴器を探しても見つからなかったら?
探しても探しても
どうして失くした補聴器が見つからないのなら購入したおm氏絵に度相談してみましょう。
補聴器によっては1年~2年程度の紛失保証がついている場合もあります。
※ただそれも1度きりが多いので、なんども無くされているとそれも使えないのですか・・・
補聴器を失くしたことで親が補聴器を使ってくれなくなるほうが困る
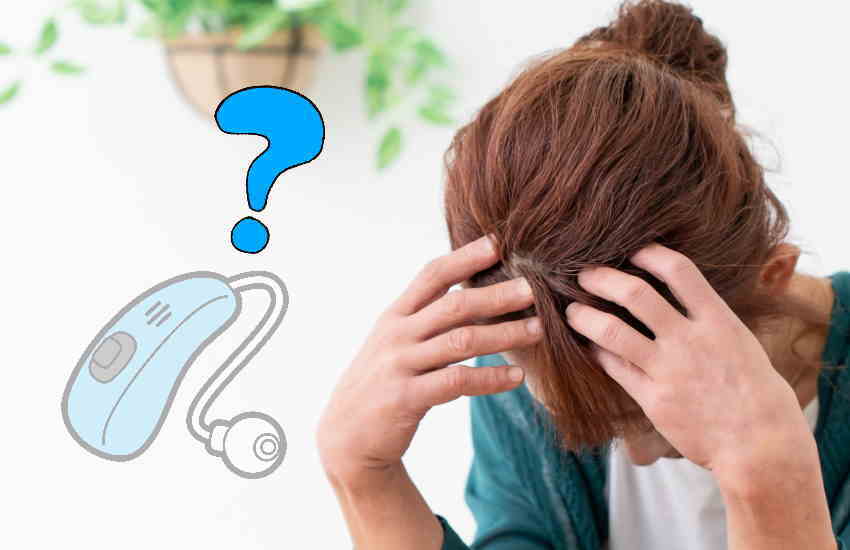
「どこでなくしたのよ!」
そう言ってきつく親を責めてはいけません。
相手は高齢者なのです。
ただでさえ歳のせいで注意力が落ちてくる野は仕方ありません。
それよりも補聴器を失くすことで、もう親が補聴器を使ってくれなくなることのほうが困ります。
何度も補聴器をなくす親に対策は難しい!ならこれを使ってもらえば?

そこでご紹介するのは補聴器ではなく集音器の「みみ太郎 SX011-2」です。
これ、補聴器というよりも昔のウォークマンみたいなやつです。
はっきりいってデカイ!
でも、これがいいんです。
これだけ大きいとなくさないんです。
しかも、操作はスイッチ兼ボリューム調整のダイヤルひとつだけ
乾電池で動きます。
※充電するために外してなくすこともよくあります。

価格は両耳用で7万円です。
確かに安くはありませんが、補聴器よりはかなり安いはずです。
このみみ太郎が高齢者には好評なのです。
【みみ太郎 ユーザーレビュー】
超小型の高価な補聴器はもう不要かも?
私は外出用の補聴器と普段使いの集音器と2つ併用はいかがでしょうか?
また高齢になればそれほど外出も少なくなるはずです。
ですから、それほど見栄えを気にしなくてもいいのではないでしょうか?
だからこのみみ太郎が良く売れているのかもしれません。

みみ太郎は無料貸し出し期間がある

とはいえ実際に購入しても親が使ってくれなかったら困ります。
ですのいでみみ太郎は無料で試せる貸出期間があるのです。
これなrた「安心して試せるのではないでしょうか?
補聴器をすぐに失くす親に対策をするの無理では?
補聴器販売店に補聴器を亡くさないようにする対策を相談しても
・補聴器に紛失防止用ストラップを付ける
・置き場所を決めて、普段そこに置くことを習慣づける
そんアドバイスしかもらえません。
紛失防止用のストラップは結構邪魔で、充電する時にはいちいち外さなければならない場合もあります。
普段から補聴器の置き場所をきちんと決めて、外したらそこに置く習慣をつける?
それができるくらいなら補聴器なんてなくしませんよね。



